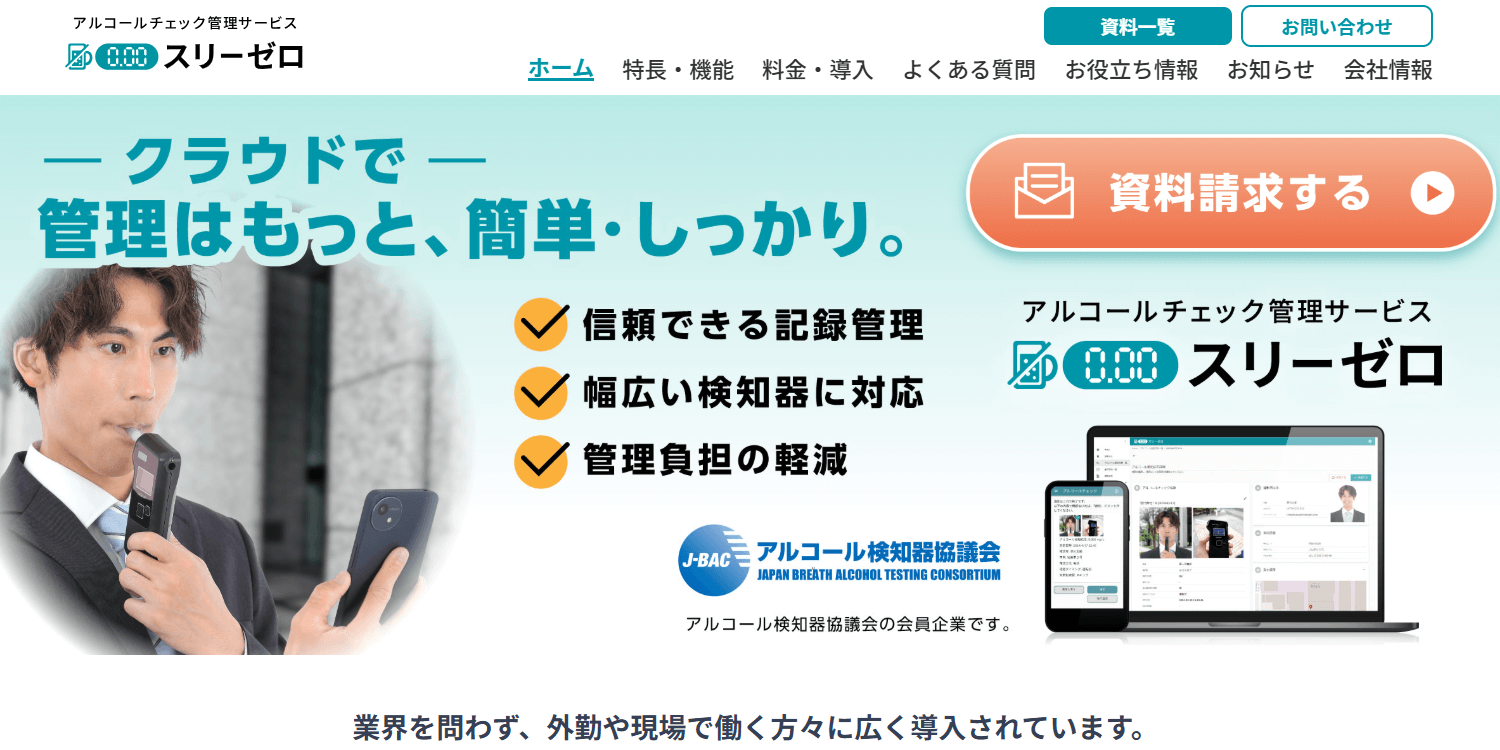ノンアルコールと表示されている飲料なら、運転前に飲んでも問題ないと考える方は少なくありません。しかし、実際にはノンアルコール飲料の中にも微量のアルコールを含むものが存在し、飲み方によってはアルコールが検出される可能性があります。この記事では、ノンアルコール飲料の定義や注意すべき点について詳しく解説します。
ノンアルコール飲料の定義
お酒を飲みたいけれど運転があるときや体に気をつけたいときに、ノンアルコール飲料を選ぶ人は多いです。しかし「ノンアルコール」と書かれているからといって、必ずしもアルコールがまったく入っていないわけではありません。まずはその意味を正しく知ることが大切です。ノンアルコールって何?
日本の法律では、アルコールが1%以上の飲み物は「お酒」として扱われます。逆に1%未満であれば、酒類ではなく「ノンアルコール」として販売できます。つまり、ノンアルコール飲料の中には、微量ですがアルコールが入っている商品もあるのです。たとえばノンアルコールビールやカクテルには、0.5%くらいのアルコールが含まれていることがあります。
注意したいこと
アルコールが少しでも入っていると、運転や体調に影響が出る場合があります。「ノンアルコール=アルコールゼロ」と思わず、ラベルを確認してから飲むと安心です。微量でもアルコールが入っていることを知っておくと、トラブルを防ぐことができます。ノンアルコール飲料を飲む際は「アルコール度数」に要注意
お酒の雰囲気を楽しめるノンアルコール飲料ですが「アルコールが全く入っていない」と思って飲むと、思わぬトラブルにつながることがあります。運転や体調管理のために飲む場合は、注意が必要です。アルコール度数を確認しよう
ノンアルコール飲料でも、微量のアルコールを含むものがあります。缶やボトルにはアルコール度数が表示されているので、運転する日は0.00%のものを選ぶのが安心です。スーパーやコンビニでは表示を見れば確認できますが、居酒屋やレストランでは判断がむずかしいこともあります。お店で飲むときのポイント
メニューに「ノンアルコール」と書かれていても、アルコールが少し入っている場合があります。運転予定があるときは、店員に「アルコールは完全にゼロですか?」と確認すると安心です。小さな注意が、思わぬトラブルを防ぐことにつながります。飲酒運転の罰則について紹介
お酒を飲んだあとに運転することは、とても危険で法律でも禁止されています。ノンアルコール飲料を選ぶ人の多くは「これなら大丈夫」と思うかもしれませんが、微量でもアルコールを含む場合は注意が必要です。ここでは、飲酒運転の種類とそれぞれの罰則について、わかりやすく紹介します。酒酔い運転
飲酒運転には大きく分けて「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があります。まず酒酔い運転は、体の中のアルコール量に関わらず、飲んだ影響で安全に運転できない状態のことを指します。たとえば、ふらつきや運転操作の乱れ、話し方や受け答えが不自然な場合などです。酒酔い運転と判断されると、罰則は非常に重く、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
また、免許は取り消され、再取得できるまでの期間は最低でも3年です。アルコール濃度が低くても、運転に支障が出る状態であれば酒酔い運転に当たるので注意が必要です。食品や調味料、喫煙などで微量のアルコールが体内に入る場合もあり、日常生活の中でも影響が出ることがあります。
酒気帯び運転
次に酒気帯び運転は、体内にアルコールが残っている状態で運転していた場合を指します。道路交通法では、呼気1リットルあたり0.15mg以上のアルコールが検出されると酒気帯び運転となります。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に加え、免許の停止や取り消しといった行政処分があります。具体的には、0.15mg以上0.25mg未満の場合は免許停止が90日以上、0.25mg以上になると免許は取り消され、欠格期間は2年以上です。酒気帯び運転も軽く見てはいけません。
ノンアルコール飲料でも注意
アルコール度数0.00%の飲料であれば、通常の飲用では体内にアルコールが検出されることはありません。しかし、微量のアルコールを含むノンアルコール飲料を短時間に多く飲むと、体質や体調によっては基準値に達する可能性があります。そのため、飲んだ直後に運転するのはリスクをともないます。ノンアルコールと書かれていても、必ずラベルの度数を確認し、安全を最優先に行動しましょう。